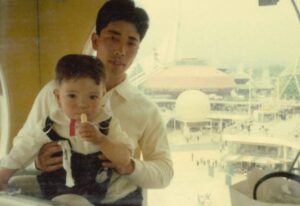鹿島道路株式会社 東北支店技師長 佐々木一夫さん
「よぉぐ来た」「んだんだ」。訪れた人を東北なまりでねぎらい、その話にじっくり聞き入る姿を知る人は多い。
古川工業高校を卒業後、建設省東北地方建設局(現・東北地整)に入省。青森・秋田・宮城・山形4県の事務所で、橋梁・道路構造物の建設と維持管理を担当した。同期入省で全国最後に係長に昇進したが、逆に最も早く建設監督官、出張所長に就いた人だ。
2011年の東日本大震災後では、地整幹部として東北6県の自治体との窓口に。支援物資から棺まで、求められれば何でも調達、提供した。
定年間際には、地整採用の星として道路保全企画官の要職に。橋梁新設時の「長期保証」導入に力を尽くした。
その一例が、PC橋の初期ひび割れ防止や、鋼橋塗装の5年保全など。
「寒冷地だから傷むのは早いと決めつけるのではなく、どのように手当てすれば長持ちさせられるのか」
退職後、現在の職場に移って10年。橋梁人へアドバイスを送り続けてきた。例えば災害調査で、例えば講演で。
2年前の豪雨災害では、河川の増水で流失した県内の橋の調査に専門家として赴き、意見を述べた。
今年5月(掲載時=2024年5月)、EARTH CREATEの勉強会では、道路橋補修で無駄使いを無くすことをテーマに講演。「損傷要因の徹底検証によってのみ、不適切な補修を回避できる」と強調し、「私たちそれぞれが、老朽化対策にどう関わっていくのか。1人ひとりが想像力を働かせて」と呼びかけた。
みちのくコンサルタント(仙台市、柴田久社長)が昨年秋(同=23年秋)、青森市で開いた勉強会での発言が印象深い。
「井の中の蛙大海を知らず、されど空の深さを知る」
荘子の言葉を紹介し、「狭い世界でも、道を究めれば、その世界の深いところまで達することができる」と受講者を励ました。
宮城県出身、70歳。
(橋梁通信第150号 2024年6月15日付掲載)
◇
橋と共に生きる橋梁人を追う「橋に魅せられて」を随時掲載しています。